リーダーシップを鍛える Leadership&Resilience【第一博愛】
今もお世話になっている、園田学園女子大学教授の荒木香織さんの本のタイトル
アメリカを代表するスポーツ心理学の権威らのもとで8年間研鑽を積み、その知見でラグビー日本代表をメンタルコーチとして支えた。アジア南太平洋スポーツ心理学会副会長を務める、スポーツ心理学における日本の第一人者。
そもそも、様々な世界における素晴らしいリーダーたちは、どちらかというと「持って生まれた資質」や「育ってきた環境」による影響が大きいと思っていた私にとっても、マインドセットを変えるきっかけとなりました。
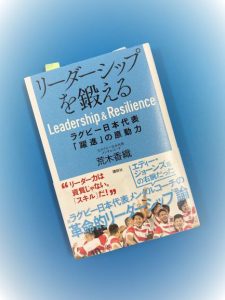
「リーダーシップの欠如、リーダー不在」
この言葉を耳にして、当事者意識を持って自身やチームを見つめ直したり「よーし私が!」と思える人が、今のスタッフにどれだけいるでしょうか?
|
Column 1 コミュニケーションの本質は「聞くこと」 ※一部抜粋(原文ママ)
コミュニケーションは、会話やお互いのやりとりだと思っていませんか? もしくは、自分が何かを発信して、相手に理解してもらう。それがコミュニケーションだと思っている人もたくさんいます。しかし本当に重要なのは、どれだけ「聞いているか」です。それは案外難しいものです。
特にリーダーには、自分の思いは伝えるけれど、フォロワーの意見はいらないという人が多いようです。あるいは、状況を把握するためにまずフォロワーから話を聞いていると主張する人もいますが、実際にきちんと話を聞いている人はそれほど多くありません。 自分の先入観や偏った価値観を持たずに、目の前の人が何を言おうとしているのかを素直に聞けるか。組織での立場が上になればなるほど、それは容易ではありません。
一方、昨今では和気あいあいとしたサークルのような、家族のような風通しのよい関係を求めるリーダーも少なくありません。和気あいあいとした愛情のある組織であれば質が高いと思われる節がありますが、メンバー同士ただ仲良くして動かそうと考えるような人は、リーダーシップの本質を理解していないと言わざるを得ません。
|
正論や最新の福祉論をスパルタ式で一方的に伝えていくのか、利用者支援より上っ面の人間関係を優先し、スタッフ同士機嫌を伺いながら仲良きことで収めてしまうのか。
いずれにしても、利用者さんにいい影響を及ぼす可能性があるコミュニケーションとは言えないでしょう。
利用者さんのグループ再編に伴い、来年度の新しいグループリーダーおよび所属スタッフが決まりました。
~新リーダーへ~
サービス管理責任者としっかりコミュニケーションを取りながら、「個人の特性を理解した上での創意工夫な方法や科学的支援」を学びながらリードしてくれることを、期待しています!
~フォローワースタッフへ~
夜勤ペアの相方として、いや支援現場におけるひとりの支援員としてだって構わない。リーダーのポジションでなくても、その言動によっては、フォロワーシップで貢献できるはずです!
年齢や性別、立場や人間関係、一博でのキャリアなどにとらわれず、利用者さんのために、もっとリーダーシップを発揮してみませんか?
「多くの方が、『私はリーダーの器じゃない、上に立つ才能はない』などとおっしゃいます。でも、リーダーシップは素質ではなく、スキルであり、鍛えることができるのです。特別な才能のある人だけが持ち合わせる「資質」ではなく、誰でも伸ばすことができる「技術」なのです」という荒木さんの言葉を信じて…
